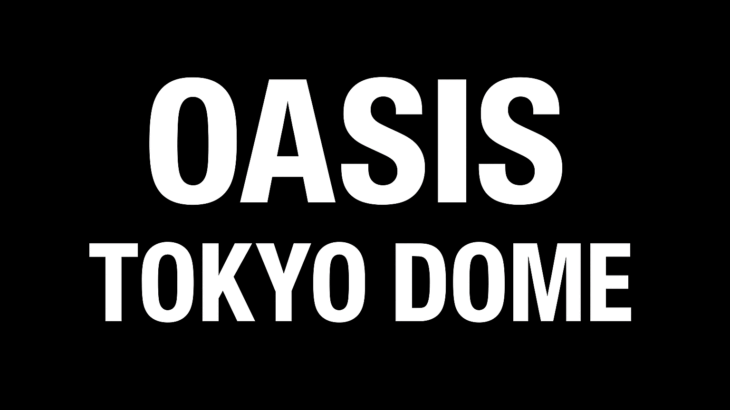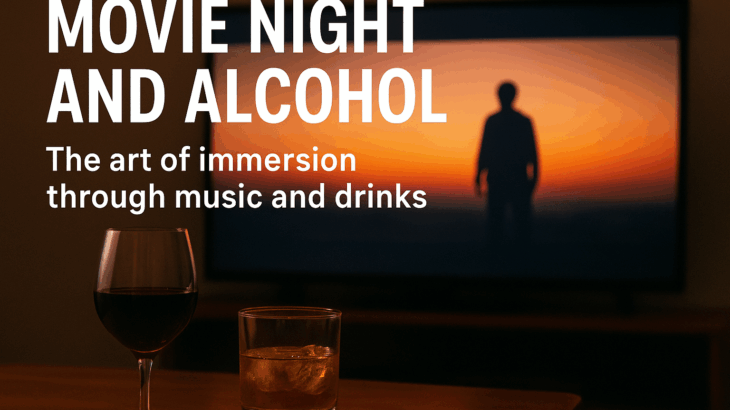はじめに
9月28日、日曜日。秦野たばこ祭り。
秋の夜風が、少しだけ冷たくなりはじめたころ。秦野の空に大輪の花火が咲く。

その音は、遠くの山々に反響し、まるで大地が応えるように低く響く。
人々はその音を胸に感じながら、手にしたグラスをそっと傾ける。
この夜、選びたいのは「ただの酒」ではない。音と光が混ざりあう、その瞬間にふさわしい「一杯」である。
それぞれの音が放つ情景に合わせて、三つの酒を選んでみた。
花火がはじまる前の静寂 ― 白ワインと余韻の序章
まだ花火が打ち上がる前、広場のざわめきがゆるやかに膨らんでいく時間。子どもたちの笑い声と、遠くの太鼓の響きが重なりあい、空気がわずかに緊張を帯びる。
この「始まりの静けさ」に合わせたいのは、冷やした白ワイン。たとえば、ソーヴィニヨン・ブランのように、柑橘と青草の香りが立つ一本。軽やかな酸が口の中をすっと抜け、夕暮れの風と溶け合うように消えていく。
白ワインは、まるでステージ前のイントロのようだ。派手ではないが、これから始まる華やぎの予感を、そっと耳元で囁いてくれる。この時間を静かに味わえる人ほど、夜の美しさを深く知っている。
夜空を焦がす光と音 ― スパークリングワインのリズムで
一発目の花火が上がる。空気が裂けるような音とともに、光が夜を貫く。その瞬間、誰もが息を止める。
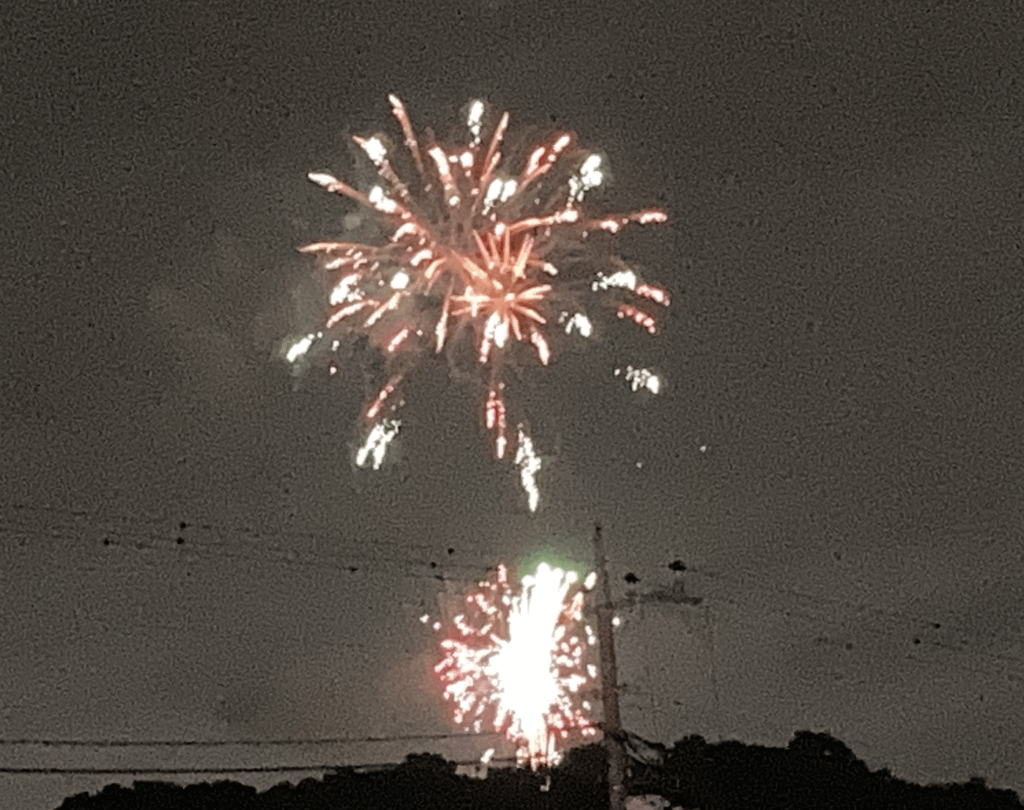
音がリズムになる。光がメロディーになる。それらが一体となって、街全体がひとつの「曲」を奏でているようだ。
花火には「爆ぜる瞬間の美しさ」と「一瞬で消える儚さ」がある。この2つを同時に内包する音楽がある。私にとってそれはやはりUnderworld。
あのゆっくりと高揚していくビート、光のように伸びるシンセのライン。たとえば “Always Loved A Film” のように、花火の音が夜に滲んでいく。
祭りのざわめきに混じって、遠くでそのリズムが聴こえてくるような錯覚。花火の上がるたびに、音の粒が空に舞い、そして消えていく。

酒は―スパークリングワインが良い。
グラスの中で立ち上る泡は、夜空に打ち上がる花火のよう。ひと口飲むたびに、胸の奥で音が弾ける。
花火の夜にちょうどいい「儚い華やかさ」をもっている。冷えたボトルを氷水に差し込み、河川敷で。コルクの抜ける音と同時に、空に打ち上がる花火。

それだけで、もうその夜は完璧だ。
終わりゆく夜と、帰り道の一杯 ― バーボンソーダと残響の記憶
花火が終わり、人々が静かに帰り始めるころ。私も帰路につく。

屋台の灯が消えはじめ、遠くで太鼓の音がまだ小さく響いている。風が少し冷たくなり、足元に夏と秋の境目の気配が漂う。

そんな帰り道に選びたいのは、バーボンソーダ。ハイボールではなく、あえてのソーダ割り。余韻を残しながら、喉をなめらかに通り抜ける甘みと煙。
琥珀の液体が、まるで花火の残光のようにグラスの底で揺れる。その味わいは、まるでラストナンバーのようにしみじみと胸に残る。祭りが終わる寂しさを、少しだけやわらげてくれる。
そして、ふと思う。
音も光も、酒も同じ「刹那の芸術」なのだ。すべてはその瞬間にしか存在しない。だからこそ美しいのだ。
おわりに ― 花火が教えてくれること
花火は、あまりに早く消えてしまう。
けれど、その一瞬の光を心に刻むために、私たちは毎年、同じ場所に集まる。
音楽も、酒も、同じだ。
すぐに消えてしまうからこそ、強く記憶に残る。その瞬間を愛でる心こそが、「大人の祭り」の愉しみなのかもしれない。
白ワインの酸、スパークリングの泡、バーボンの甘み。
それらが、今年の花火の音と混ざり合い、この秋の夜を少しだけ豊かにしてくれる。
今夜の空に上がる光は、きっともう一度は戻らない。
けれど、あの音と香りの余韻だけは、しばらくのあいだ、私の胸の奥で小さく鳴り続けるのだ。