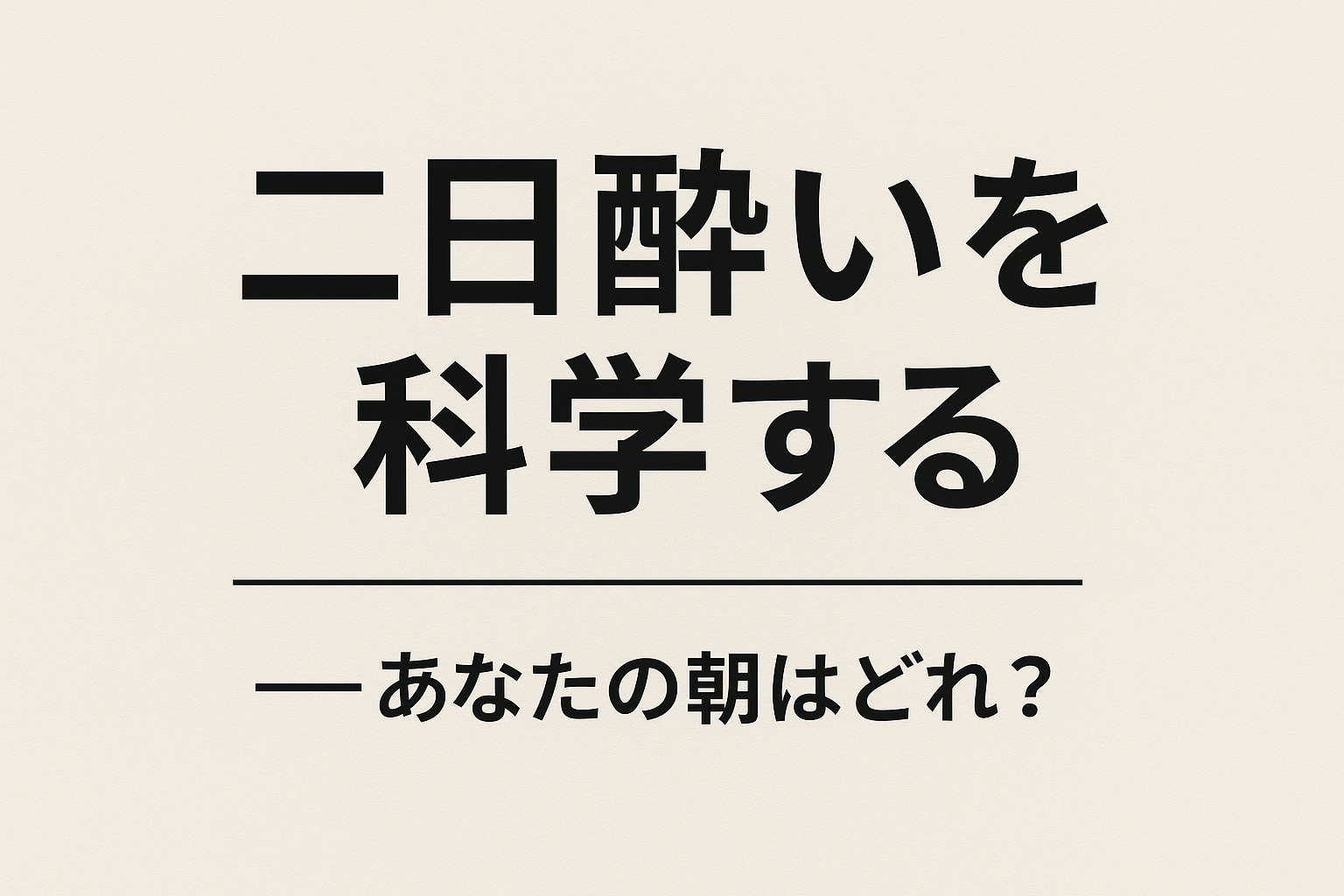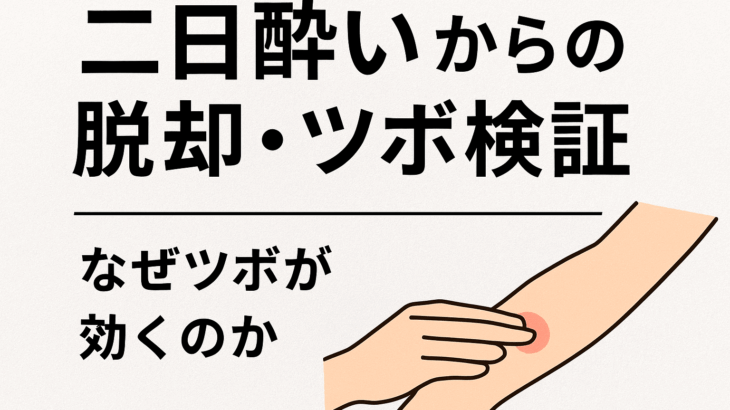はじめに
お酒をたしなむ方にとって、肝臓はまさに“沈黙の相棒”です。
何も言わず、何も訴えず、ただひたすらにアルコールを分解し、体を守り続けてくれる。
しかし、私たちはその沈黙をいいことに、つい過信してしまいます。
今回は、そんな肝臓をいたわりながら、翌朝のダメージを減らす“食べ方”について考えてまいります。
アルコール分解は「食べたか・食べなかったか」で決まる
アルコールが体に入ると、まず肝臓でアルコール脱水素酵素(ADH)が働き、それをアセトアルデヒドという物質に変えます。
このアセトアルデヒドこそが、頭痛や吐き気、倦怠感といった二日酔いの原因。
そして最終的に「酢酸」へ分解されて体外に排出されるまでの間に、肝臓は大量のエネルギーを消費します。
ここで大切なのが、飲酒前後の食事です。
空腹状態では血糖値が下がりやすく、肝臓がアルコールの分解に集中しすぎて、グリコーゲン(肝臓内のエネルギー貯蔵)が枯渇しやすくなります。
その結果、翌朝に感じる「異常なだるさ」や「冷え感」は、実は低血糖状態によるもの。
つまり、“飲む前に何かを食べる”という行為は、単なる予防策ではなく、肝臓に「燃料を補給しておく」行為なのです。
飲む前におすすめの“肝臓食”
肝臓がアルコールを分解するためには、以下が欠かせません。
・たんぱく質(特にシステインを含むもの)
・ビタミンB群
・糖質
そのため、飲む前の軽い食事には、次のようなものが理想的です。
- 冷奴+ごはん少々:大豆のたんぱく質とビタミンB群が肝臓をサポート。
- 卵かけご飯:卵のシステインがアセトアルデヒド分解を助けます。
- 味噌汁+おにぎり:塩分・糖分・ミネラルを同時に摂取できる“黄金コンビ”。
また、飲酒前に牛乳を一杯飲むのも理にかなっています。
諸説ありますが、脂肪分が胃壁をやさしくコーティングし、アルコールの吸収をゆるやかにしてくれるのです。
飲みながら意識したい“中盤の工夫”
飲みの最中こそ、実は肝臓を守る最大のチャンスでもあります。
アルコール代謝には時間がかかりますから、飲みながら「少しずつ栄養を補う」ことが効果的です。
おすすめは、以下のもの。
- 枝豆(ビタミンB1・メチオニン)
- 冷やしトマト(カリウム・リコピン)
- 鶏の塩焼き(たんぱく質)
- 味噌きゅうり(塩分+発酵食品)
これらはすべて、分解を助け、電解質のバランスを整える食材。飲み放題の場でも、このあたりを意識するだけで翌朝の調子がまるで違ってきます。
翌朝のリカバリー食は“やさしい糖質+スープ”
翌朝、体が重い・頭がぼんやりするというときは、肝臓がまだグリコーゲンを十分に回復できていない証拠です。
そんな時は、無理に固形物を詰め込まず、まずは温かい味噌汁やお粥を。ゆっくりと糖分が吸収されることで、肝臓が再び働き出します。
さらに理想的なのは、以下のもの。
- しじみ汁:オルニチンが肝臓のアンモニア処理を助ける
- 卵スープ:良質なたんぱく質で分解酵素を補う
- 梅干し入り湯:胃を刺激せず、塩分とクエン酸を同時補給
このあたりを組み合わせると、まるで“体の奥がゆるやかに再起動する”ような感覚を味わえます。
「飲む」と「整える」は、ひとつの習慣
肝臓は“鍛える”よりも“守る”臓器です。
トレーニングのように強化するものではなく、小さなケアを重ねて、本来の機能を保つもの。
だからこそ、飲み方や食べ方の工夫こそが、最良の「肝臓トレーニング」なのです。
お酒を楽しみながら、自分の体と対話する―そんな意識を持つだけで、二日酔いの質も、翌朝の気分も大きく変わります。
最後に
五回にわたってお届けした「二日酔いを科学する」シリーズ。最後にたどり着いたのは、結局とてもシンプルな真理でした。
“体をいたわることは、飲むことを深く味わうことでもある”
お酒をただ楽しむのではなく、身体の声を聴きながら「飲む」「整える」「生きる」を丁寧に重ねていく。
その先に、きっと健やかな酔いの世界が広がっているのだと思います。