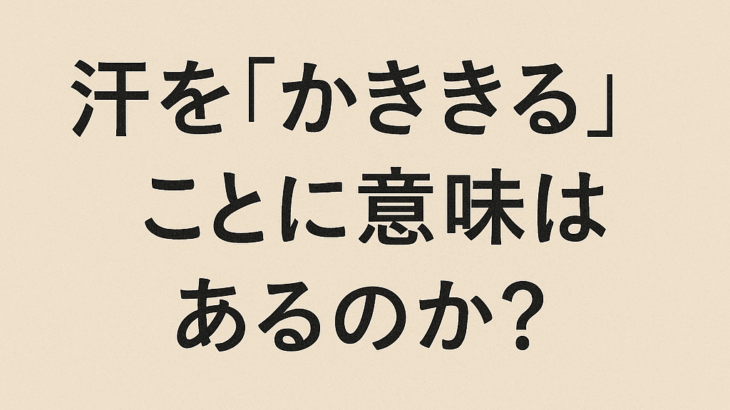サウナでは「汗をかききる」べきなのか
サウナが好きで通っておりますと、ふとした疑問が湧いてまいります。
「サウナって、汗をたくさんかいた方が良いのだろうか?」
あるいは、「汗をかききって“出し切った”感覚が大事なのか?」という問いです。
本日は、このテーマについて、発汗の仕組みや身体の反応に触れながら、少し丁寧に考えてみたいと思います。
汗を「かくこと」と「かけること」は別物
結論から申し上げますと、サウナにおいて大切なのは、たくさん汗をかくことそのものではなく、「汗がかける身体」になっているかどうかです。
つまり、しっかり汗腺が反応してくれているか、そのことの方が、よほど重要だということになります。
発汗の仕組みー汗腺と体温調節
人間の身体には、200万個から500万個ほどの汗腺が備わっているとされております。
しかしながら、そのすべてが常に活躍しているわけではありません。普段からよく使われている「能動汗腺」と呼ばれる汗腺だけが、日々の生活で働いています。
この汗腺、実は乳幼児期(おおよそ3歳まで)に環境によって“育つ”と言われておりまして、大人になってからは、使わなければ機能が落ちてしまうこともあるのです。
たとえば、冷房のきいた環境で長く過ごしていたり、運動不足が続いていたりしますと、汗腺の働きは鈍りがちになります。
サウナの効能「汗をかける身体」への再教育
このように、鈍ってしまった発汗機能を、もう一度目覚めさせてくれる。それがサウナのもたらす効用の一つです。
サウナに入りますと、体温が一時的に上昇し、汗をかこうとする身体の仕組みが自然と動き出します。これを繰り返すことで、汗腺が再び“能動化”され、汗をかきやすい身体へと整っていくのです。
そのため、「滝のように汗を流す」ことにこだわる必要はございません。むしろ、うっすらと汗ばむ程度でも、身体がきちんと反応しているのであれば、それで十分なのです。
「出し切る」感覚の正体とは?
では、よく耳にする「出し切った!」「全部出た気がする!」というあの爽快感。
あれはいったい、何が起きているのでしょうか。
実はこれは、医学的に見ると、以下のような状態を指していると考えられます。
- 交感神経が優位だった状態(サウナ)から、副交感神経が優位な状態(休憩・外気浴)に切り替わった
- 血流が促進され、筋肉のこわばりがほどけた
- 呼吸が深くなり、心拍数が落ち着いた
つまり、「整う」というあの独特な感覚は、自律神経の切り替えがうまくいったときの身体のサインなのです。
「汗がたくさん出たから整った」のではなく、“切り替えが成功した”結果として、快感がやってきたという方が、より正確な理解かもしれません。
汗で“毒素”は出るのか?
ここでひとつ、サウナにまつわる誤解についても触れておきましょう。
「汗をかけば毒素が出る」という言い方をよく耳にします。
たしかに、汗には微量の老廃物や重金属が含まれていることは事実ですが、その大半(99%以上)は水分と塩分であり、“デトックス”の主役は腎臓や肝臓といった臓器の方です。
とはいえ、汗をかくことによって体温調節が促され、代謝が上がり、自律神経のバランスも整うという副次的な健康効果は、間違いなく存在しております。
まとめ「出すこと」より「反応すること」を大切に
サウナに入った際、「今日はあまり汗が出なかったな」とがっかりする必要はありません。大切なのは、「入ったことで身体に何が起きたか」を感じ取ることです。
- 少しの時間で身体が温まった
- 呼吸がゆっくりになった
- 外気浴で自然と目を閉じたくなった
そんな小さな兆しこそが、サウナが“効いている”証拠なのだと思います。
ぜひ、「汗をたくさんかく」ことにとらわれず、身体がどう反応するか、どんな変化があるか。その過程を楽しみながら、サウナの時間をお過ごしいただければと思います。