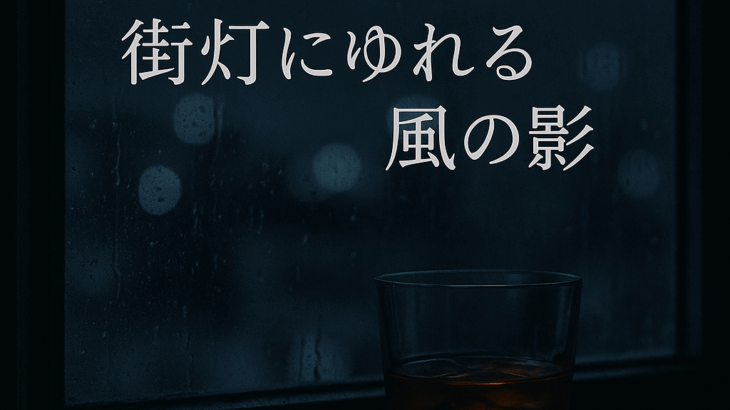夜も深くなってまいりました。
街のざわめきも途絶え、道路を走る車の音も、まばらに遠ざかるばかり。そんな時間帯になると、不思議と人の感覚というものは、日中とは異なる形で研ぎ澄まされてまいります。
静まりかえった部屋の中、ほんの少しだけ開けた窓から、風がふわりと流れ込んでまいりました。エアコンでは到底代替できない、自然の空気。生きている風です。
その風は、無理に押し入ってくることなく、ただこちらの心の準備が整うのを待っているかのように、静かに、ゆっくりと部屋の隅々をなぞっていきます。まるで、見えない何かが「今夜の空気はどうだろうか」と、こちらを伺っているような感覚。
扇風機の風は均一で、どこか人工的な整いを持っておりますが、夜風は異なります。ほんの一瞬だけ強く吹いたかと思えば、次の瞬間にはすうっと抜けてゆき、またふたたび、気まぐれに戻ってくる。
不規則でありながら、自然のリズムの中ではしっかりと意味を持っている。そう思えるのが、夜の風なのです。
このような静けさの中、私はひとつの所作としてグラスに手を伸ばします。氷の入ったグラスに、ほんの少しだけウイスキーを注ぎ、その香りをじっくりと確かめる。そのとき、ふわりと夜風が頬をかすめ、グラスの中にまで入り込んでくるような気がいたします。
夜風には、記憶を呼び覚ます力もあります。
学生時代に深夜の公園で語り明かした友人との会話。誰もいない駅のホームで、一人で飲んだ缶ビールのぬるさ。旅先の宿で、窓の外をそよいでいた潮風の湿った匂い。
そんな過去の時間が、突然目の前に浮かんでくるのです。
街灯に照らされたアスファルトの揺らぎ。風に押されて揺れる洗濯物の影。向かいのアパートの階段に、一瞬灯る足音。
これらすべてが、夜の風の中で、音もなく一枚の絵になっていく。
そこにグラスを重ねるという行為は、まさに詩のようなものだと感じております。
酒というものは、単体でも確かに豊かな味わいを持っておりますが、それを取り巻く空気や温度、そしてこの「風」の存在によって、さらにその奥行きを増していく。
夜風とは、酒の背景をつくりだす名脇役であり、時には主役の一部でもあるのかもしれません。
今夜の酒:ラフロイグ10年
アイラ島で生まれた、強烈な個性を持つ一本。グラスに注ぐと、すぐに立ち上るスモーキーな香り。まるで古びた灯台の階段をのぼるような、潮と木と焚き火が混じり合ったような香りが鼻腔をくすぐります。
その個性ゆえに好みが分かれるラフロイグですが、夜風と共に味わうことで、そのとがった部分が角を丸め、驚くほど深く、そして穏やかな味へと変化いたします。
風が運ぶ塩気と、ウイスキーのスモークが織りなす一瞬の調和。まるで、長い旅のあとにふと立ち寄った灯台の下、海を眺めながら過ごすひとときのよう。
今宵もまた、風に抱かれながら、ひとり乾杯を。過去と現在を行き来しながら、静かに味わう夜が、そっと更けてまいります。