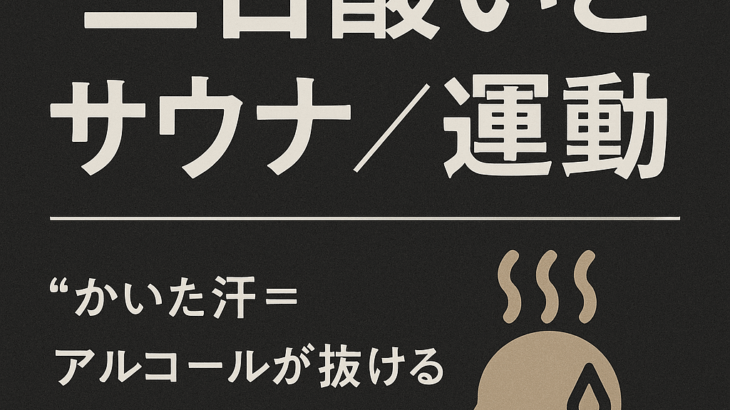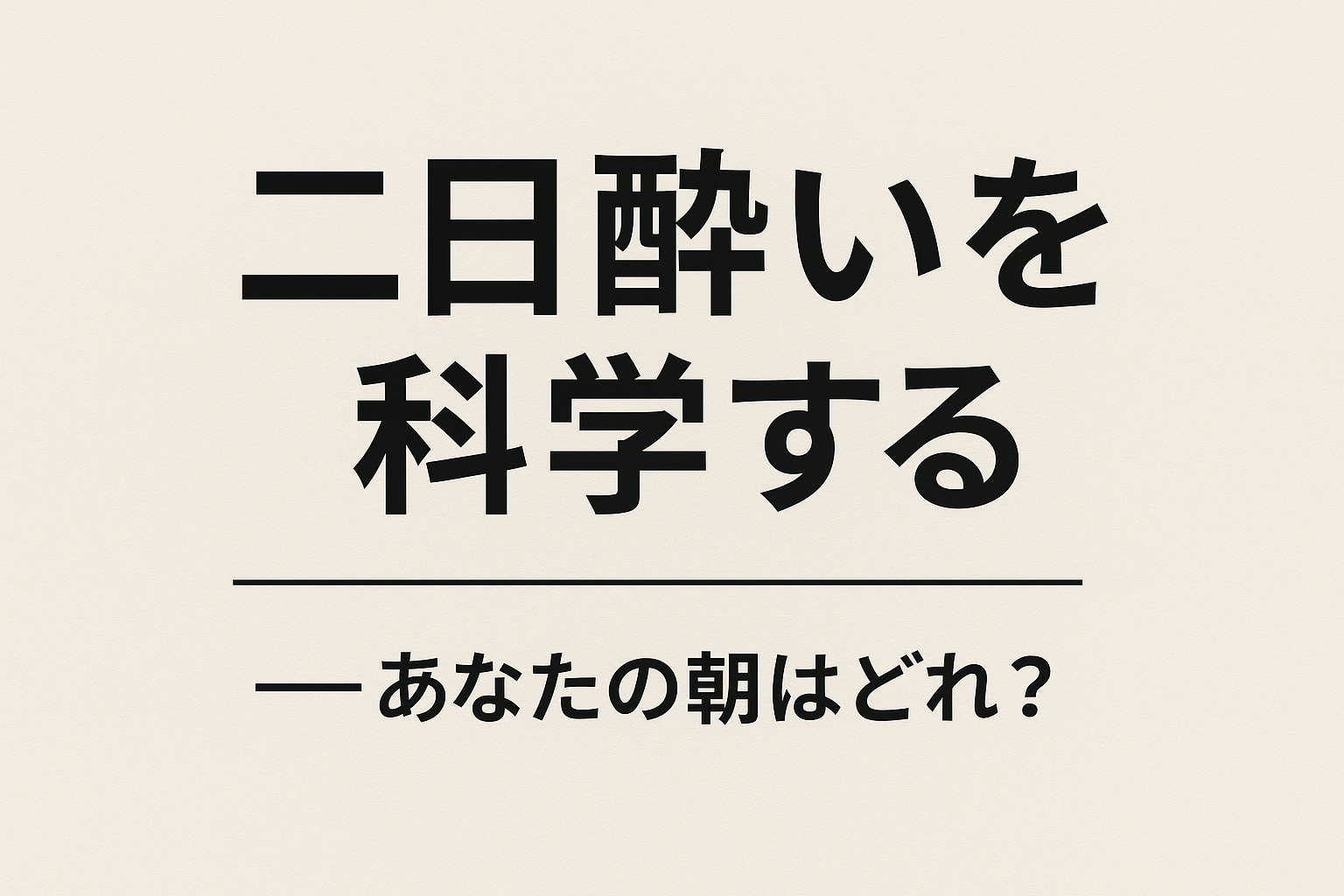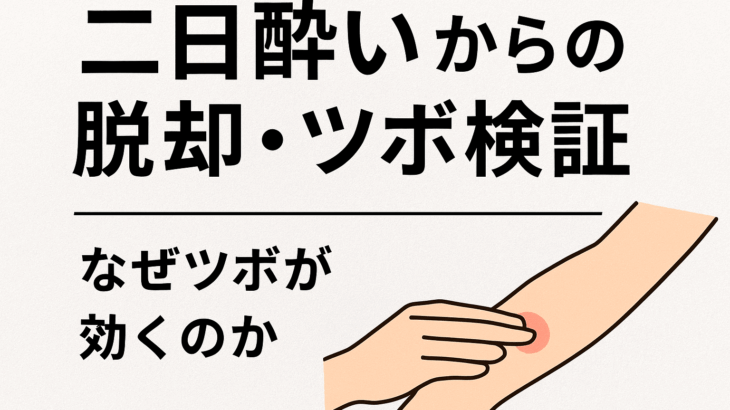「汗でアルコールは抜けるのか?」を静かに考える
「サウナに入れば酒が抜ける」「走って汗をかけば二日酔いが治る」
そうした言葉を耳にしたことのある方もいらっしゃるかもしれません。
実際、私自身も飲みすぎた翌日にサウナへ行くと、少し頭がすっきりしたように感じることもあり、それが「酒が抜けた」感覚として感じることもあります。
しかしながら、実際に汗をかくことでアルコールそのものが体から抜けていくのか?と問われれば、そこには慎重な視点が必要です。
本記事では、サウナや軽い運動が「二日酔いの回復に与える影響」を科学的に整理しつつ、誤解を招かぬよう穏やかなトーンで解説してまいります。
汗で「アルコールが抜ける」は本当か?
結論から申しますと、アルコールの大部分(約90〜95%)は肝臓で代謝され、残りは呼気・尿・汗として排出されると言われています。
つまり、汗にも微量のアルコールが含まれることは事実です。
けれど、そこから期待される「排出量」はごくごくわずかであり、汗をかいたからといって体内のアルコールが著しく減るわけではありません。
実際に体内に残るアルコールの量を減らすには、時間と代謝(肝臓の働き)が最も重要であり、これは、サウナや運動ではコントロールできない部分であります。
なぜ「抜けたように感じる」のか?
それでは、なぜ私たちは「サウナに入ったら楽になった」「汗をかいて体が軽くなった」と感じるのでしょうか?
その答えは、自律神経の調整にあります。
アルコールを摂取すると、自律神経のバランスが乱れがちになります。とくに交感神経と副交感神経の切り替えがうまくいかず、ぼんやりとした頭痛や倦怠感、胃の不快感などが長引くことも。
ここでサウナや運動を行うと、以下のような反応が起きます。
- 体温の変化による血行促進
- 一時的な交感神経の活性化(→ その後の副交感神経優位のリラックス状態へ)
- エンドルフィンなどの脳内ホルモンの分泌増加(快感・覚醒の要因)
これらが組み合わさることで、身体や頭が軽くなったように感じられ、「酒が抜けた」という主観的な印象に繋がるのだと考えられます。
注意すべきポイント:「脱水」と「心負担」
しかし、ここで大切なのは、サウナや運動が必ずしも“安全”とは限らないという点です。
アルコールの摂取後は、以下のようなリスクがあります。
- 脱水状態になりやすい(アルコールに利尿作用があるため)
- 心拍数や血圧が変動しやすい
- 判断力・平衡感覚が落ちている可能性がある
このような状態で長時間のサウナや無理な運動をすると、かえって体調を崩してしまう危険性もあります。とくに飲酒後12〜18時間以内の強い発汗行為については、慎重な判断が求められます。
あくまでも「整える」という視点で
私自身、飲んだ翌日にサウナに行くことがあります。
しかしその際には、「酒を抜く」のではなく、「整える」ことを目的にしています。
具体的には
- サウナは短時間・1〜2セットのみ
- 水分はしっかりと摂る(水 or 白湯)
- サウナ後は静かな場所でゆっくり過ごす
- 身体に熱がこもる感覚があれば、すぐに中止する
これはあくまでも「回復のきっかけを与える」程度の働きであり、アルコールの代謝そのものは自然な時間経過に任せるしかないという前提を、忘れてはならないようにしています。
慎重に、そして自分の声を聴く
サウナや軽い運動には、確かに気分を整える力があります。
けれど、それを「抜ける」と表現したり、万能薬のように扱うことは避けたいところです。
大切なのは、「無理なくできる範囲で、体調のバランスを取り戻す」という視点。そして何より、“今日はちょっと無理だな”という自分の感覚に従うことです。
二日酔いの朝こそ、身体は多くの声を発しています。その声に耳を澄ませながら、慎重に、そして静かに自分自身に向き合ってまいりましょう。