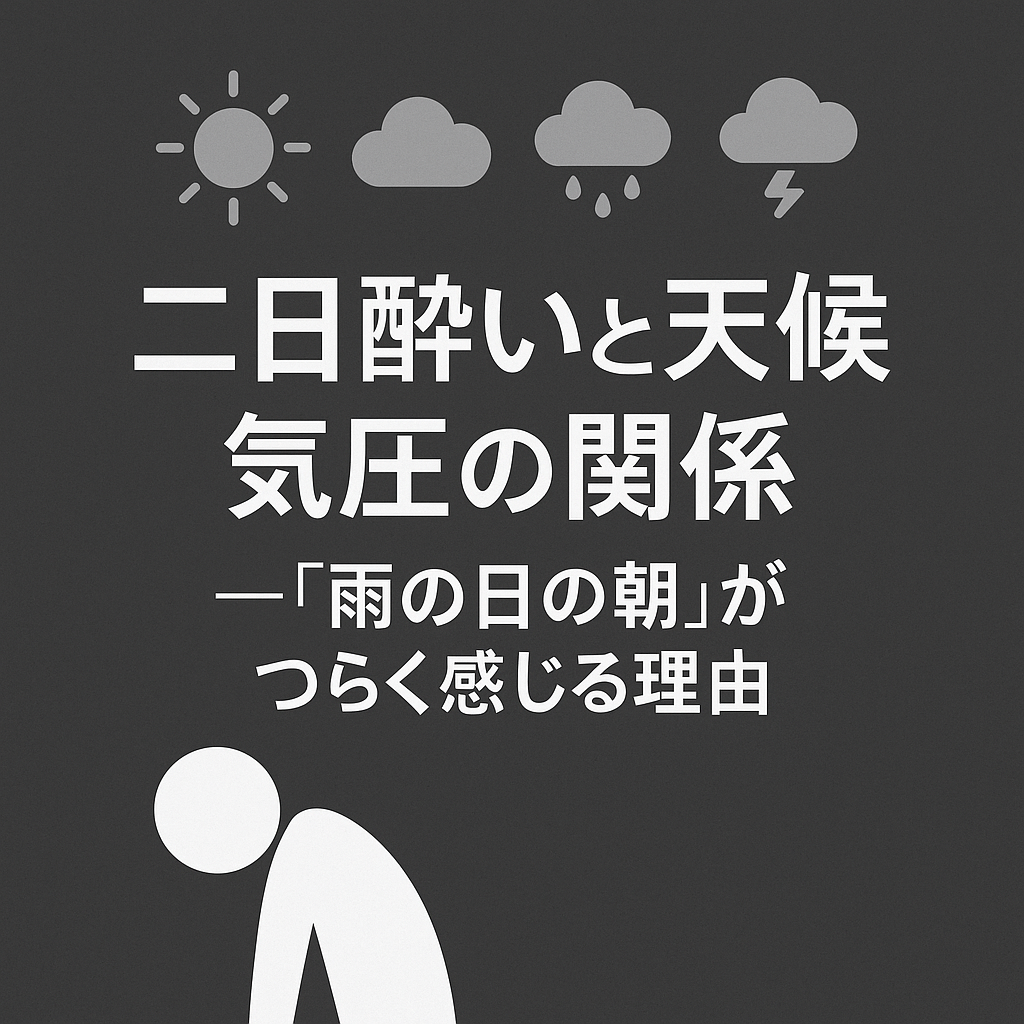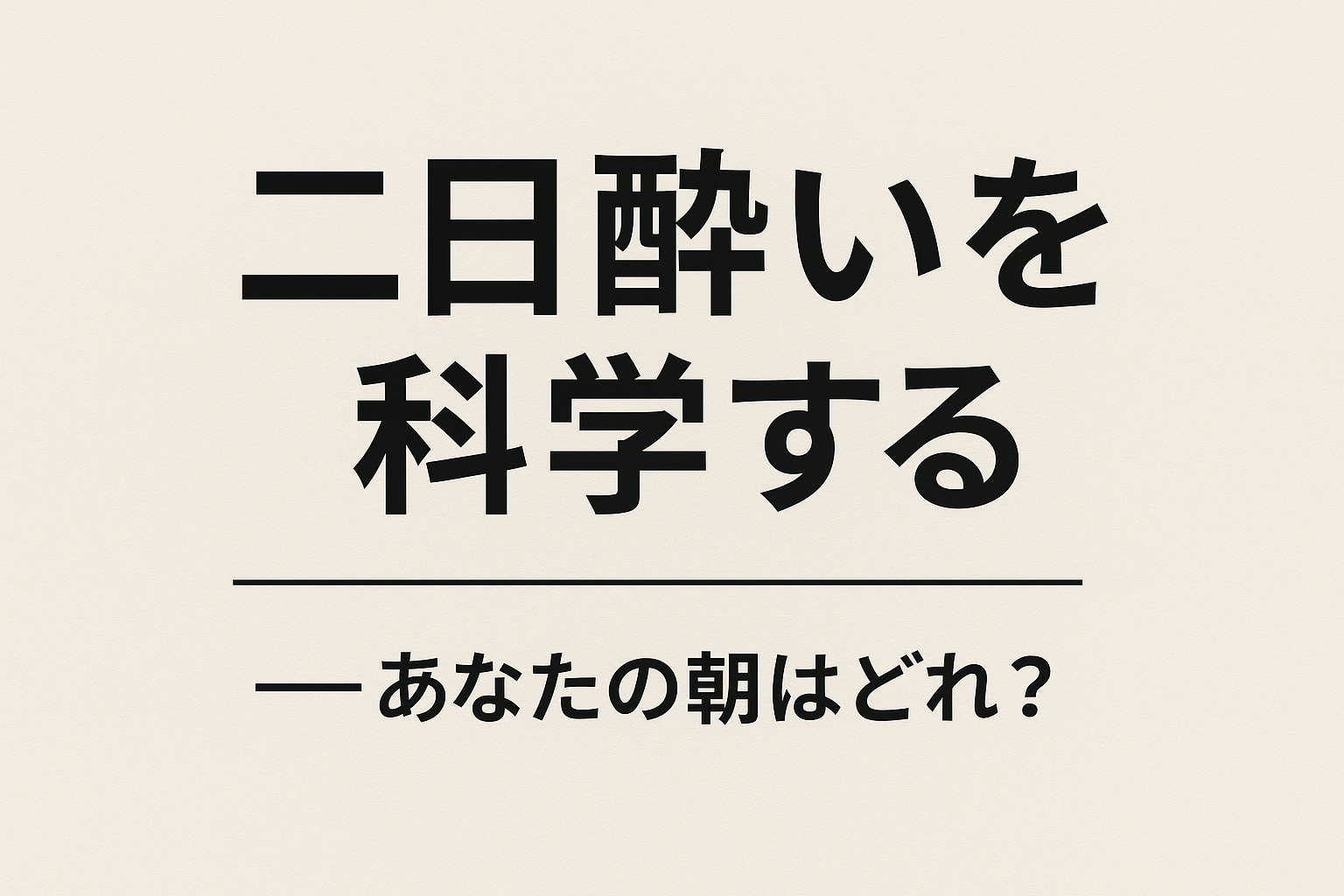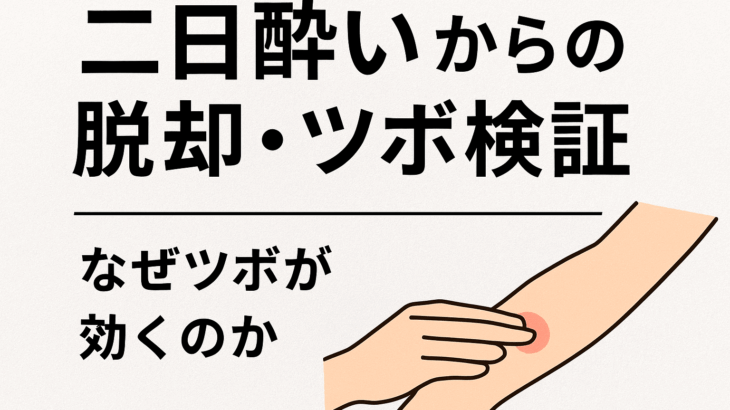「雨の日の朝」がつらく感じる理由
同じように飲んだはずなのに…「今朝は妙に重いな」と感じる日があります。
その朝、ふとカーテンを開けると、窓の外はどんよりと曇っていたり、小雨が降っていたり。湿気を含んだ空気が、身体にまとわりつくような、あの鈍い重さ。
経験的に、「天気が悪い朝は二日酔いが重く感じる」という方も多いのではないでしょうか。
今回はその不思議な関係性を、自律神経や気圧の変化など、身体の内側から丁寧にひも解いてまいります。
気圧の低下と自律神経のバランス
まず前提として、私たちの体調は、気圧や気温、湿度といった「天候の変化」に大きく影響を受けています。
特に「気圧の低下」は、自律神経の働きを乱しやすいことで知られています。気圧が下がると、私たちの身体は副交感神経が優位になり、リラックス状態に傾いていきます。
それだけ聞くと「良いこと」のように思えますが、アルコールの影響でそもそも神経系が鈍っている状態では、この「副交感神経優位」が、さらなる倦怠感や眠気、頭のぼんやり感を引き起こすことがあります。
いわば「ぼんやり+ぼんやり」で、身体がますます目覚めづらくなるわけです。
酸素の取り込みも、地味に減る
気圧が下がると、空気中の酸素濃度もわずかに低下します。
この変化は登山のような高地で顕著ですが、実は日常の天候の変化でも、私たちの身体は微細に反応しています。
二日酔いのとき、身体は「アルコール代謝に必要な酸素」を大量に使って回復を試みています。そんなタイミングで酸素の供給がわずかでも減ると、当然その代謝効率も落ちてしまい、いつも以上に回復が遅れることがあるのです。
これが「雨の日の二日酔いは抜けにくい」と感じる一因とも言えるでしょう。
湿度と体感の重さー身体にこもる熱
梅雨時や雨の朝、なんとなく「身体の熱が抜けにくい」「頭が重い」と感じることがございます。湿度が高いと、汗が蒸発しづらく、熱が体内にこもりやすくなるためです。
二日酔い時の「身体のだるさ」には、体温調整の乱れも大きく関係しています。特にアルコールは一時的に末梢の血管を拡張させ、体温を下げにくくする傾向があるため、湿度が高い環境ではこの状態がさらに強調され、「なんとなくずっと火照っている」「脱ぎたくても脱げない重たいコートを着ているような感じ」になることもあるのです。
季節による違い:「夏の朝」と「冬の朝」
個人的な体感ではございますが、季節によっても二日酔いの「質」には違いがあります。
- 夏の朝の二日酔い
→ 湿度の高さで熱が抜けにくく、重く、ぼんやりとした感覚が長引く。
→ 冷房の中では冷えすぎて胃が動かず、余計に気持ち悪さが強まることも。 - 冬の朝の二日酔い
→ 空気が乾燥しており、体内の水分が失われやすい。
→ 寝ている間の「脱水」が進み、朝起きたときに喉がカラカラ、頭がガンガンということが多い。
どちらも一長一短があり、それぞれに対策が必要だと感じております。
対策:天候に応じた「回復の設計」
以下に、天候別のおすすめ対策を簡単にまとめておきます。
【雨の日・湿度が高い朝】
- 温かい白湯をゆっくり飲む(内側から循環を促す)
- 湿度でこもった熱を逃がすため、軽くストレッチや換気をする
- 胃腸が重いときは、味噌汁や梅干し湯などで塩分と水分を整える
【乾燥して寒い冬の朝】
- まず水分をたっぷり(白湯またはぬるま湯で)
- 湯船につかって内臓から温める(可能なら朝風呂も◎)
- 手足が冷たいと感じたら、あえて靴下をはいて保温
「天気のせいにする」ことの大切さ
二日酔いの日は、つい自分を責めたくなってしまうものです。「昨日飲みすぎたなあ」と、自己嫌悪の中に沈んでしまうこともあるでしょう。
けれど、そんなときは、「今日は気圧が低いせいだ」「天気のせいで重たいんだ」と、一歩引いてみるのもひとつのやさしさかもしれません。
天気も、身体も、思い通りにはならないけれど、それを知ったうえで、自分に合った朝の過ごし方を少しずつ整えていく。
それが、健やかにお酒と付き合っていくための、ひとつの術ではないでしょうか。